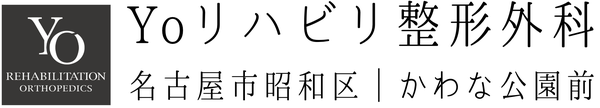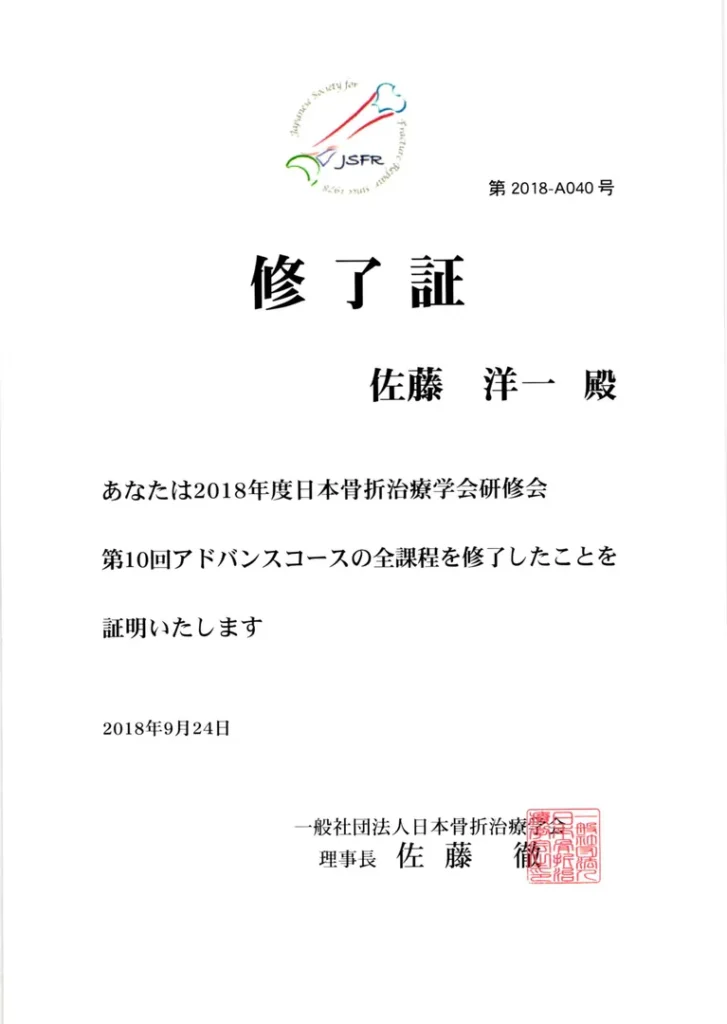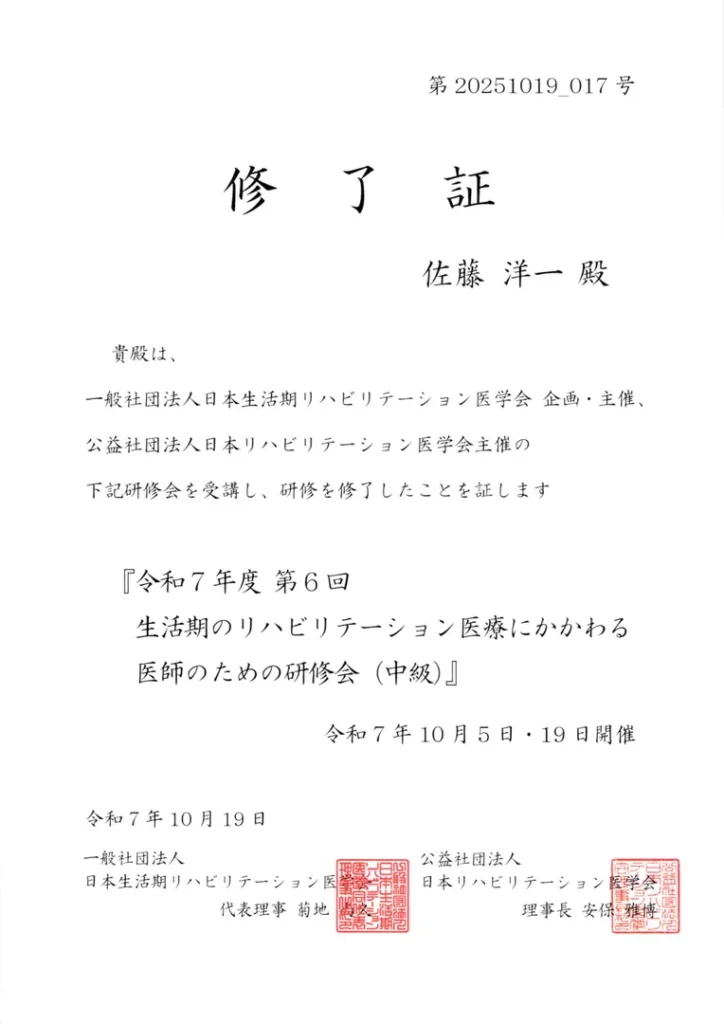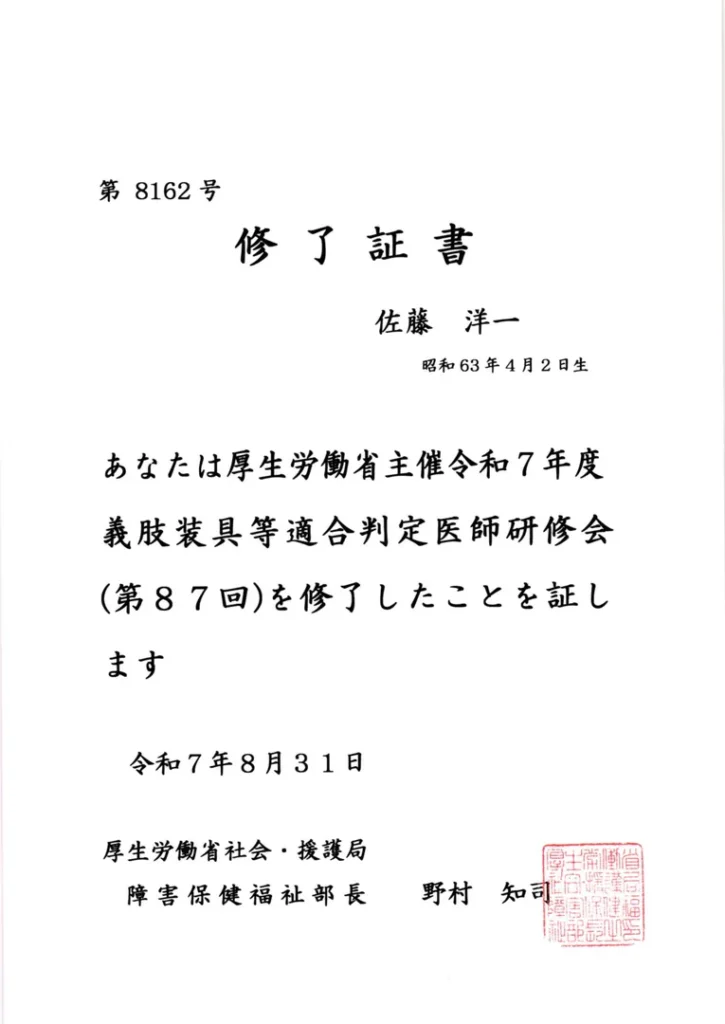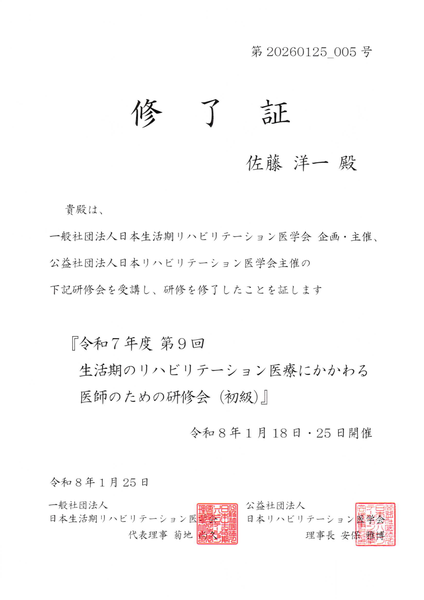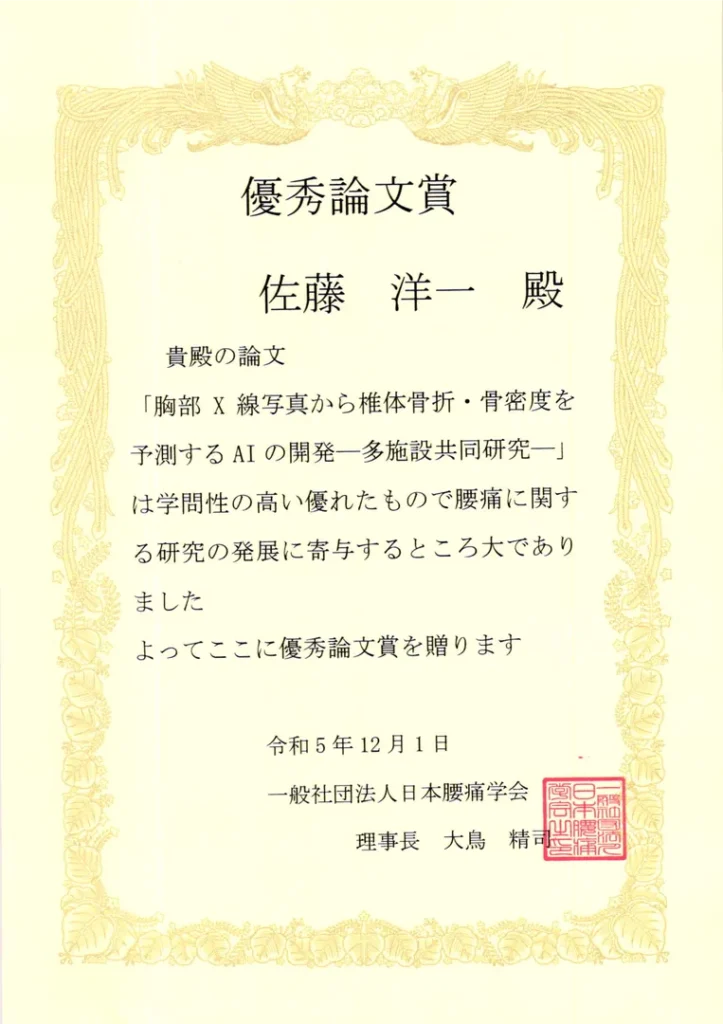この記事の要点
- 日本語タイトル:鏡視下腱板修復術後リハは断裂サイズでどこまで個別化される?
- 英語タイトル:Rehabilitation protocols after arthroscopic rotator cuff repair: A survey of active members of the Korean Shoulder and Elbow Society.
ここで取り上げるのは、肩の手術後のリハビリについて、整形外科やリハビリテーション科の外来でよく話題になる内容です。
医学用語が多い分野ですが、できるだけ日常の言葉に置きかえてお伝えします。
研究の背景・目的
「鏡視下腱板修復術(きょうしか けんばん しゅうふくじゅつ:Arthroscopic rotator cuff repair)」とは、肩の関節を小さなカメラと器具でのぞきながら行う、腱板(けんばん:肩の深いところにある筋肉と腱の集まり)の修復手術のことです。
この手術のあとに行う「リハビリテーション(rehabilitation:機能回復のための訓練やケア)」は、再び腱が切れてしまうことをできるだけ防ぎ、肩の動きや力を取り戻していくうえで、とても大切な部分です。
しかし、どの患者さんにも同じように当てはまる「標準的なリハビリの進め方(標準化プロトコル)」は、まだはっきり決まっていません。
特に、腱板の「断裂サイズ(どのくらい大きく切れていたか)」や、患者さんの日常生活・仕事・スポーツなどの「活動性(体をどれくらい使う生活か)」によって、どこまでリハビリの内容や進め方を変えるべきかが、議論になっている点です。
調査の方法(対象など)
この研究では、「韓国肩・肘学会(Korean Shoulder and Elbow Society:肩と肘の病気を専門に扱う医師の学会)」に所属する、積極的に活動している会員140名の医師に、インターネットを使ったアンケート調査が行われました。
そのうち113名が回答し、いずれも肩を専門とする整形外科医でした。
アンケートでは、医師としてどのくらいの年数、肩の診療をしてきたかといった経験年数に加えて、「外転装具(がいてん そうぐ:肩を少し外側に開いた位置で腕を支える固定用の装具)」を使うかどうか、その装具でどのくらいの期間固定するか、リハビリをいつから始めるかなど、具体的なリハビリの進め方(プロトコル)について詳しくたずねています。
研究の結果
回答した医師は全員(100%)、手術後に外転装具を使用していました。
また、約93%の医師が、腱板の断裂サイズ(切れていた大きさ)によって、外転装具で固定しておく期間を調整していました。
「中等度断裂(moderate tear:小さすぎず、大きすぎない中くらいの大きさの断裂)」の患者さんでは、多くの医師が、まず外転装具での固定を続け、装具を外したあとに「関節可動域(かんせつ かどういき:Range of Motion, ROM:肩がどこまで動くかの範囲)」の訓練を始める、という流れをとっていました。
さらに、「筋力トレーニング(strength training:筋肉の力を鍛える運動)」については、手術からおよそ3か月後に開始するやり方が、多くの医師で共通している実態が示されました。
結論:今回の研究でわかったこと
この調査から、腱板の断裂サイズ(どのくらい大きく切れていたか)と、患者さんの身体への負荷(どれくらい体を使う生活か)を考えながら、手術後のリハビリの内容や進め方を調整している医師が多い傾向がうかがえます。
特に、外転装具をどう使うか、その装具をいつ外すか、そしてリハビリをいつから始めるかといった点が整理されており、各医療機関が自分たちの「術後リハビリの決まりごと(自院プロトコル)」を考えるときに、参考にしやすい情報といえます。
実際の診察ではどう考えるか
実際の診察では、腱板の断裂サイズ(手術で修復した部分の大きさ)と、患者さんの仕事やスポーツの強さ・頻度などの「負荷の大きさ」を組み合わせて、手術後のリハビリの内容や、仕事・スポーツへの復帰時期を一人ひとりに合わせて考えていく、という発想が大切になります。
この研究で示された情報は、医療機関が自分たちのリハビリの進め方を見直すときに、現場で使いやすい具体的な参考材料になると考えられます。
参考文献
-
Rehabilitation protocols after arthroscopic rotator cuff repair: A survey of active members of the Korean Shoulder and Elbow Society.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41713723/
※この記事は、医学論文の内容を一般向けに解説したものです。診断や治療の最終判断は、必ず主治医とご相談ください。